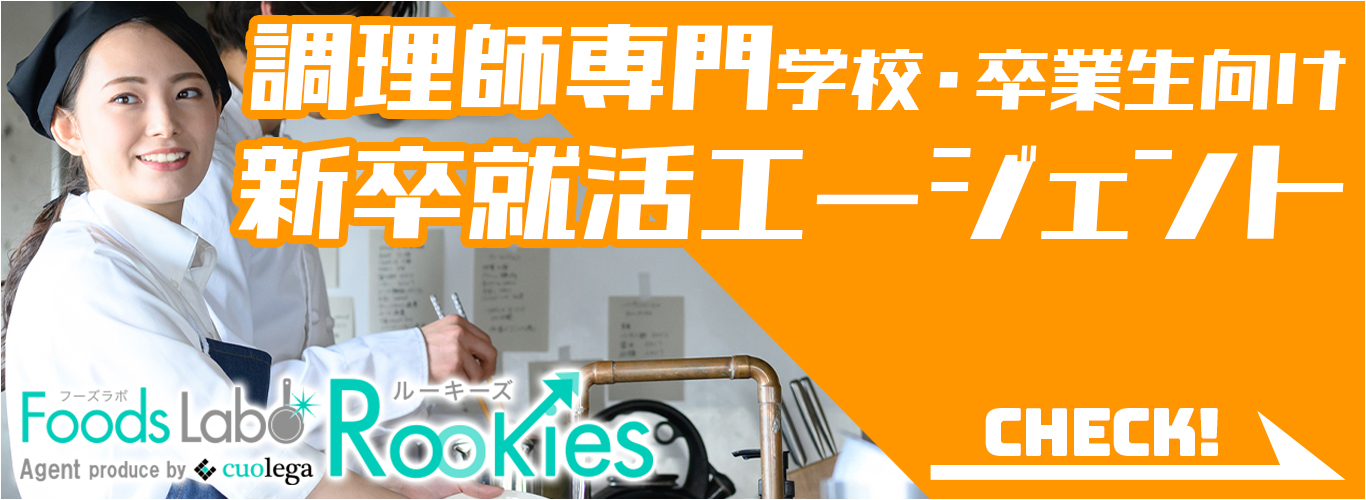若者から大人まで多くの人が好きなラーメン。
その中でも好みの麺の太さってきっとありますよね?
ちなみに私は太めが好きです。あの歯ごたえと食べ甲斐のある食感がたまりません。
今回は、そんなラーメンの重要な麺についてとことん調べました。若者から大人まで多くの人が好きなラーメン。その中でも好みの麺の太さってきっとありますよね?ちなみに私は太めが好きです。あの歯ごたえと食べ甲斐のある食感がたまりません。今回は、そんなラーメンの重要な麺についてとことん調べました。

まず、麺は何から作られているかご存じですか?
意外と知らない人もいるのではないでしょうか。正解は、小麦、水、かん水です。
【小麦】一般的にラーメンなどの中華麺は専用の強力粉か準強力粉が使われます。
この小麦粉の違いはタンパク質含有量(グルテン)の割合です。
強力粉はパン、パスタに主に使われ準強力粉などが中華麺に使われます。一口に小麦粉と言っても、こだわりを持って麺づくりに使われています。
【水】次に水にもこだわりがあります。
私も好きな豚骨ラーメンのようなドロッとしたスープには硬水が使われ、一方で煮干しや野菜のようなあっさりした味がウリのスープには軟水が使われているのです。
スープのテイストによって味を変えるひと手間が美味しいスープの素になっています。
【かん水】最後のかん水ですが、知らない方も多いのではないでしょうか。
かん水とは炭酸ナトリウムや炭酸カリウムなどを指しており麺にハリやツヤを与える役目があります。中華麺独特の風味や色合いはこのかん水を加えて茹でた後にできるのです。
また、このかん水の代わりに重曹を使われることもあるそうです。
ここまで主なラーメンの麺の原料について触れましたが、続いては食感に大きな影響をもたらす水の量について詳しく見ていきましょう。
ラーメンの中でも食感が全然違うものがありますよね。
その理由は小麦粉を練る際に使用される水の量にあり、その割合を加水率と呼びます。
そして、この加水率が高い麺のことを「多加水麺」と言い、低いものを「低加水麺」と言います。
まず、多加水麺とは先ほどの加水率の割合が35%以上の麺を指し、特徴としてスープを吸収しいくい、スープに絡みにくい、麺があまり伸びないことが挙げられます。
加水率が高いことによって、モチモチした食感で麺は柔らかいのですが、スープに絡みにくいため、濃厚なこってりとしたスープとの相性は抜群です。そのため、具材やスープと一緒に食べるというイメージが近いですね。
一方の低加水麺は加水率30%以下で、スープを吸収しやすいうえに絡みも良く、小麦粉の味がストレートに反映されて麺が伸びやすいことが特徴です。一般的には加水率の低い麺は水分を吸うので、デメリットとしては伸びやすいですが、博多ラーメンのように短時間で食べて替え玉をする形式が向いているとされています。
続いては麺の太さについてです。
ラーメンの味にも関わってくる重要な要素ですが、切刃番手という規格が定められていてそれに基づいて番号も割り振られています。
この番号は、太さ30mmの麺を何本に切り分けられるかという考えがベースです。この切刃番手の番号に当てはめて麺の太さは決まります。
【極細麺・細麺】ここからは極細麺、細麺、中細麺、中太麺、太麺、極太麺の順に切刃番手に当てはめてみます。まず、28番~30番で太さ1.1mm~1.0mmの麺で、22番~26番で太さ1.4mm~1.15mmの麺は細麺です。
極細麺や細麺は、ツルっとしている分喉越しと歯切れが良くスープとよく絡むので、あっさりとしたラーメンとの相性抜群です。
【中細麺・中太麺】次の中細と中太麺は普通麺とも呼ばれ、20番で太さ1.5mmとされています。
細麺と太麺との丁度中間くらいの太さなので一番シンプルな太さですね。中細麺と中太麺が好きな方も多いのではないのでしょうか。
【極太麺・太麺】最後に、10番~14番で太さ3.0mm~2.2mmの麺は極太麺、16番~18番で太さ1.875mm~1.7mmの麺は太麺とされています。
細い麺と違ってコシのあるモチモチとした食感が特徴的で、つけ麺などの濃厚なスープやこってり系のスープに良く合います。 麺の太さは感覚で考えてしまうと個人差が出てしまいますが、切刃番手で定量的に判断すれば誰でも同じ基準で認識ができますね。
麺の作られ方から太さまで様々な違いがあることはわかりましたが、麺といえば、ちぢれている方がいいのか、はたまたストレートの方がいいのかという話もちらほら聞いたことがあります。この二つの違いはスープへの絡み方です。
ストレート麺は、麺が細いため麺と麺の間が非常に狭くそこにスープが入り込むとそのまま留まるので、結局麺に絡むスープの量が多くなるのです。
一方のちぢれ麺は、切り刃にシリコンゴムのプレートを着けて切ることで麺に不規則な力が加わってちぢれます。このちぢれ麺は、麺と麺の間に広い隙間があいてしまいせっかく吸い上げたスープの膜が割れて下に落ちてしまいます。よって、ストレート麺の方がスープをちゃんと味わいたい方にはお勧めというわけです。

私はふと疑問に思ったことがあります。そもそも麺の原価は何円なのでしょうか。
結論から言うと一杯分100gの麺で50円ほどです。驚きの安さですね(笑)
ただ質の良い製麺店から仕入れて、手もみ式などこだわりの製法を取り入れれば取り入れるほど原価は高くなり、一杯あたり30%程度のコストアップにもなります。
ここにスープや具材も入ってきて味の種類によっても多少値段は変わりますが、だいたい醤油ラーメンで約185円、味噌ラーメンで約270円、豚骨ラーメンで約215円となります。
味噌ラーメンの原価が高くなる理由としてはポーションが挙げられます。つまり一皿当たりの分量です。豚骨ラーメン一杯のスープ量が、浅めのドンブリに入れるため300ccである一方で、味噌ラーメンはその1.5倍の450ccの分量になります。この分が原価に跳ね返っているのです。常に長蛇の列を作るラーメン屋は原価率が良ければ、かなりの利益が出ているのではないでしょうか。
今回はラーメンの麺について詳しくまとめました。
麺は小麦、水、かん水が原料で小麦に加えられる水の量で麺の食感にも違いが生まれます。そして、麺の太さは切刃番手によって基準化されており、極細から極太まで分けられています。
さらに、ちぢれ麺とストレート麺でも相性の良いスープが異なるのでこだわりがありましたね。このようにしてできる麺の原価はおよそ100gで50円ほど!ですが、ラーメンの種類によって使用される具材も変わるので、ラーメンとしての相場はその種類によって変わります。
このように麺の作られ方やそれぞれの麺の特徴を噛みしめながら、ラーメンを食べると味の感じ方が少し変わるかもしれませんね!